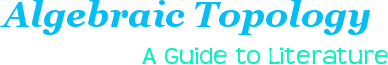
| date | page |
|---|---|
| Nov 01 | generalized_manifold... |
| Nov 01 | cobordism_category.h... |
| Nov 02 | t-structure.html |
| Nov 03 | origami.html |
| Nov 03 | amplituhedron.html |
| Nov 03 | generalized_polytope... |
| Nov 04 | spectral_sequence.ht... |
| Nov 04 | spectral_sequence_in... |
| Nov 05 | physics_and_algebrai... |
| Nov 06 | homotopical_algebrai... |
| Nov 06 | condensed_object.htm... |
| Nov 06 | etale_homotopy.html |
| Nov 07 | infinite_dimensional... |
| Nov 08 | Adams-type_SS.html |
| Nov 08 | unstable_ASS.html |
| Nov 09 | homotopy_set.html |
| Nov 09 | noncontinuous.html |
| Nov 10 | profunctor.html |
| Nov 10 | category.html |
| Nov 10 | monad.html |
| Nov 11 | derived_algebraic_ge... |
| Nov 12 | MU.html |
| Nov 12 | manifold.html |
| Nov 12 | formal_group_law.htm... |
| Nov 13 | calculus.html |
| Nov 14 | generalized_string_t... |
| Nov 15 | history_of_mathemati... |
| Nov 16 | graded_algebra.html |
| Nov 16 | Koszul_duality.html |
| Nov 17 | Frobenius_algebra.ht... |
微積分学と解析学の初歩 |
|
微分積分学は, 線形代数と共に, 大学入って最初に学ぶ数学であり, 現代数学の基本の一つである。 (代数的) トポロジーの重要な概念も元をただせば微分積分学に辿りつくものが多い。 関手の微積分のように, 初等的な微分積分学からアイデアを得た理論もある。 複素解析 (関数論) の方がより幾何学的であるが。 有名な教科書として Spivak の [Spi06] がある。 私は読んだことはないが。 Newton と Leibniz により17世紀にその理論が構築された, とされているが, 彼等は, 微分積分学の基本定理を「発見」しただけで, 正確な証明を行なったわけではない。 実数の定義が無かったので当然であるが。 一方, 彼等以前にも同様のアイデアは様々な人により追求されていたようである。 例えば, この Numberphile の動画によると, 14世紀から15世紀にインドの Kerala 州にあった Kerala School of Mathematics and Astronomy では, 三角関数やそれらの逆関数の Maclaurin 展開が考えられていたようである。 それ以外の関数は考えられていなかったようであるが。 この動画では, Divakaran という物理学者により書かれた本 [Div18] が紹介されている。 ICM 2022 の proceedings にも Ramasubramanian による論説 [Ram23] がある。 References
|